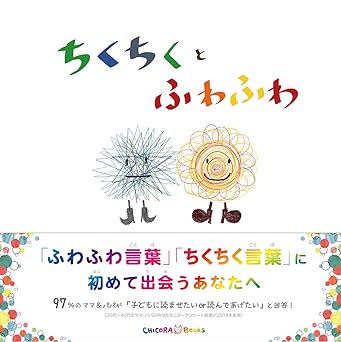「ふわふわ言葉とちくちく言葉とは?」
「ふわふわ言葉の例は?」
子供と過ごす毎日の中で、「言葉のかけ方」で悩んだことはありませんか。励ましたい気持ちで声をかけたのに、子供がしょんぼりしてしまった経験を持つ方もいるのではないでしょうか。実は、子供の心をあたたかく包む「ふわふわ言葉」と、傷つけてしまう「ちくちく言葉」があります。どちらを選ぶかによって、子供の気持ちや自己肯定感の育ち方は大きく変わります。
この記事ではその違いや実践方法を解説します。子供と過ごす中で言葉の掛け方に悩んでいるかたは、ぜひ参考にしてください。
※2025年9月9日時点の情報です。
ふわふわ言葉とは?
子供との関わりで使われる「ふわふわ言葉」とは、聞いた人の気持ちをやさしく包み込み、安心感や喜びを与える言葉のことです。保育や子育ての現場では、子供の自己肯定感を育てる大切な言葉かけとして重視されています。
ふわふわ言葉の特徴
ふわふわ言葉には「ありがとう」「うれしいよ」「がんばったね」など、相手の行動や存在を認める表現が多く含まれます。これらは子供の気持ちを前向きにし、「自分は大切にされている」という実感を持たせる効果があります。
ふわふわ言葉の効果は?
日常的にふわふわ言葉をかけられた子供は、安心して自分を表現できるようになります。その結果、挑戦する意欲が高まり、人との関わりにも積極的になる傾向が見られます。また、失敗しても「次はがんばろう」という前向きな気持ちを持ちやすく、粘り強さを育む効果も期待できます。さらに、家庭や保育の中で繰り返し伝えられることで、信頼関係が深まり、子供は「大人に受け止められている」という安心感を得られます。
甘やかしとの違い
ふわふわ言葉は「なんでも許すこと」や「叱らないこと」とは異なります。いたずらや危険な行為に対しては、大人がルールを明確に伝える必要があります。たとえば「走らないで!」ではなく「ここは歩こうね」と行動を具体的に指示することが大切です。やさしさとけじめを両立させることで、子供は安心しながらも社会のルールを学ぶことができます。
ちくちく言葉とは?
「ちくちく言葉」とは、相手の心を傷つけたり、不安や悲しみを与えてしまう言葉を指します。大人が何気なく口にしたひとことでも、子供にとっては大きな影響を与える場合があります。
ちくちく言葉の具体例
「どうしてできないの?」「あっちいけ」「バカ」など、叱責や否定的な表現が代表的です。大人にとっては注意や指導のつもりでも、子供には「自分はダメなんだ」と受け止められてしまうことがあります。
子供への影響
ちくちく言葉が続くと、子供は自信を失いやすく、人との関わりを避けたり挑戦する気持ちが弱まることがあります。小さな積み重ねが心の傷となり、自己肯定感を下げる要因となるため、注意が必要です。
日常でのふわふわ言葉の実践例一覧
ふわふわ言葉は、子供の気持ちをやさしく包み、安心や自信を育てます。以下では家庭と保育・学校で使いやすい言葉を、シーンごとに具体的にまとめました。
家庭で使えるふわふわ言葉(10例)
- 朝の支度:「自分で着替えられてえらいね」
- 食事のとき:「おいしそうに食べてくれてうれしいよ」
- 片づけをしたとき:「おもちゃをしまってくれて助かったよ」
- 手伝いをしたとき:「お皿を運んでくれてありがとう」
- 挑戦したとき:「やってみようとする気持ちがすてきだね」
- 失敗したとき:「最後までがんばったのがすごいよ」
- 落ち込んでいるとき:「気持ちを教えてくれてありがとう」
- けんかの後:「仲直りできてよかったね」
- 寝る前:「今日も一緒に過ごせて幸せだよ」
- 日常のひとこと:「大好きだよ」
家庭での言葉は、日常の行動や気持ちを受け止めることが大切です。
保育や学校で使えるふわふわ言葉(10例)
- 発表のとき:「みんなの前で話せて立派だったよ」
- 友達と遊ぶ姿を見て:「一緒に遊んであげてやさしいね」
- 友達にやさしくしたとき:「やさしい気持ちがすてきだね」
- 集団生活で:「友達と仲良くできてえらいね」
- 運動の場面:「一生けん命走ってかっこよかったよ」
- 挑戦したとき:「難しいのにあきらめなかったね」
- 手伝いをしたとき:「片付けをしてくれて助かったよ」
- 失敗したとき:「次は失敗しないようにがんばろう」
- 休み時間:「とっても楽しそうだったね」
- 存在そのものに:「みんなが楽しく過ごせるのは○○さんがいてくれるからだね」
保育や学校の現場では、子供の努力や存在を認める言葉が、安心して行動できる環境づくりにつながります。
日常思わず使ってしまうちくちく言葉の実践例一覧
ちくちく言葉は、大人が注意や指導のつもりで使ってしまうものです。ここでは、よく使ってしまう言葉と、子供の気持ちを育むふわふわ言葉への言いかえ例を紹介します。
家庭で思わず出てしまうちくちく言葉の言いかえ(10例)
- 「早くしなさい!」 → 「もうすぐ出発だから急ごうね」
- 「好き嫌いばかりしてダメでしょ」 → 「頑張って一口食べてみよう」
- 「何回言ったらわかるの?」 → 「もう一度一緒にやってみようか」
- 「どうしてできないの?」 → 「ここまでできたね、次はこうしてみよう」
- 「こんなこともできないの?」 → 「少しずつ練習すればきっとできるよ」
- 「だから無理だって言ったでしょ」 → 「挑戦したことがすごいよ」
- 「じっとしてなさい」 → 「今はお話を聞く時間だよ。終わったら質問しよう」
- 「悪いのはあなたでしょ」 → 「どうしてそうしたのか聞かせてね」
- 「またやったの?」 → 「次はどうすればうまくいくかな?」
- 「ほんとに困った子ね」 → 「○○(行動)をしてくれると嬉しいな」
保育や学校で思わず出てしまうちくちく言葉の言いかえ(10例)
- 「どうしてできないの?」 → 「ここまで頑張れてえらいね」
- 「声が小さい」 → 「もう少し大きな声で聞かせてほしいな」
- 「下手だね」 → 「練習したらもっと上手になるよ」
- 「みんなできてるのに」 → 「ゆっくりで大丈夫だよ、先生待ってるね」
- 「まだ終わってないの?」 → 「もう少しでできそうだね」
- 「なんで持ってこないの?」 → 「次は準備をしっかりして持ってこれるかな?」
- 「またトラブルを起こしたの?」 → 「なんでそうしたのか教えてくれる?」
- 「真面目にやりなさい」 → 「集中できるかな」
- 「そんなの簡単でしょ」 → 「少しずつ上手になってきたね」
- 「問題ばっかり起こして」 → 「困ったときは相談してね」
親や大人の言葉遣いの心構え
子供にふわふわ言葉を届けるためには、大人自身の姿勢や心の持ち方がとても重要です。子供は大人の言葉を敏感に受け止め、繰り返し耳にすることで自分の価値を判断していきます。そのため、日々の声かけを意識的に見直すことが、子供の健やかな成長につながります。
感情を整える工夫
忙しさや疲れから、思わず強い言葉を発してしまう場面は誰にでもあります。そんなときは、まず自分の気持ちを整えることが大切です。深呼吸をして落ち着く、少し距離をとってから声をかけるなど、大人が感情をコントロールできれば、余計なちくちく言葉を減らせます。感情に任せた叱責は、子供にとって必要以上に重く心に残ることがあるため、冷静な対応を心がけましょう。
言葉を選ぶ意識
注意や叱りが必要なときでも、表現を工夫することで子供の受け止め方は変わります。例えば「走らないで!」ではなく「ここは歩こうね」と伝えると、禁止ではなく次の行動への指針となり、安心感を持って行動できます。行動を具体的に示す言葉は、子供の理解を助け、前向きな学びにつながります。
大人が見せる姿勢
大人自身がふわふわ言葉を使っている姿を見せることも効果的です。家族や友人に「ありがとう」「助かったよ」と伝える習慣を持つことで、子供は自然にまねをし、思いやりある言葉を身につけていきます。大人の言葉選びが、子供にとって最も身近な手本になるのです。
子供へのふわふわ言葉の教え方
ふわふわ言葉は、大人から子供への一方的な声かけで終わらせるのではなく、子供自身が自然に使えるようになることが大切です。自分の言葉が相手を喜ばせたり、安心させたりする経験を積むことで、子供は「言葉には力がある」と理解できるようになります。そのためには、日常生活の中で意識的に伝え、体験させる工夫が欠かせません。
モデルとなる姿を見せる
子供は大人のまねをすることで多くを学びます。家庭や保育の場で、大人が「ありがとう」「助かったよ」「うれしいよ」といった言葉を周囲に自然にかける姿を見せることが一番の教材になります。例えば、親同士が感謝の言葉を交わす様子を見せると、子供も同じ場面でふわふわ言葉を使えるようになります。
場面ごとに練習を取り入れる
ごっこ遊びやロールプレイを通じて、具体的な場面でふわふわ言葉を練習することも効果的です。おもちゃを貸してもらったら「ありがとう」、遊びを手伝ってもらったら「うれしいよ」と声に出して言う練習をすると、実際の生活の中でも自然に使えるようになります。
絵本や活動を活用する
ふわふわ言葉やちくちく言葉を題材にした絵本を読むと、子供は言葉が持つ影響を直感的に理解できます。読み聞かせのあとに「どんな言葉を言ったら友達が喜ぶかな?」と問いかけることで、考える力も育ちます。また、折り紙や工作など共同活動の中で「ありがとう」を使う場面を意識的に設けると、体験を通じて学べます。
言葉を使えたときに認める
子供が実際にふわふわ言葉を口にしたときは「やさしい言葉を言えたね」と具体的に伝えることが大切です。行動を認められると、子供は「また言ってみよう」と思うようになり、日常の中で定着していきます。
ふわふわ言葉が学べるおすすめの絵本3選
ふわふわ言葉やちくちく言葉は、子供が人との関わり方を学ぶうえで欠かせないテーマです。ここでは、家庭でも楽しく学べる絵本や児童書を紹介します。親子で一緒に読み進めることで、自然とやさしい言葉づかいが身につきます。
対象年齢:4歳~
サイズ:18.8 x 0.9 x 18.8 cm
ページ:32ページ
「ふわふわことばでなかよくなるほん (おしえて!サンリオキャラクターズ)」は、サンリオキャラクターたちと一緒に、ふわふわ言葉の大切さを学べる絵本です。「ありがとう」「だいすき」といった身近な言葉が、相手の気持ちを温かくすることをキャラクターのやり取りを通して伝えています。カラフルなイラストとやさしい文章で、子供でも理解しやすく、言葉の影響を直感的に感じ取れます。家庭での読み聞かせにも適しており、親子で言葉のやり取りを見直すきっかけになる1冊です。
対象年齢:3歳~
サイズ:20 x 20 x 0.7 cm
ページ:32ページ
「ちくちくとふわふわ」は、子供同士の関わりの中で生まれる「ちくちく言葉」と「ふわふわ言葉」を、物語仕立てでわかりやすく描いた絵本です。なないろさんのやわらかいタッチのイラストと、松本えつをさんの読み聞かせを意識した構成により、子供が感情移入しやすいのが特徴です。実際に読んだあと「こんな言葉を言ったらどう思う?」と親子で話し合うことで、思いやりや言葉の選び方を考える習慣づけができます。園や学校での道徳教育の題材としても活用できる内容です。
対象年齢:3歳~
サイズ:18.7 x 1.1 x 20.7 cm
ページ:56ページ
「ことばいいかええほん: ふわふわとちくちく」は教育学者の齋藤孝氏が監修し、言葉を「ちくちく」から「ふわふわ」にどう言い換えるかを具体的に紹介した本です。「うるさい!」を「ちいさなこえでおはなしして」と言い変えるなど、実生活でそのまま活用できる表現が豊富に載っています。川原瑞丸さんの温かみあるイラストが、子供にも大人にも親しみやすい雰囲気を与え、言葉を選ぶ大切さを楽しく学べます。家庭の読み聞かせだけでなく、先生や保育士が指導に取り入れる教材としても役立つ1冊です。
まとめ|ふわふわ言葉で子供の未来をつくる
ふわふわ言葉とちくちく言葉は、子供の心の成長に大きな影響を与える言葉です。ふわふわ言葉は安心感や自己肯定感を育て、子供が挑戦する気持ちを支えます。一方で、ちくちく言葉は自信を失わせ、関わりを避ける原因となることもあります。家庭や保育の場で実践例を取り入れながら、子供自身がふわふわ言葉を使えるようサポートすることが大切です。また、甘やかしとの違いを意識し、必要な場面ではルールを具体的に伝えることも忘れてはいけません。日々の言葉の選び方が、子供の未来を豊かにしていきます。
#ふわふわ言葉 #知育ママ #知育 #3歳 #4歳 #低学年
▼参考文献
立川女子高等学校.“「ふわふわ言葉」と「チクチク言葉」”.https://www.tachikawa-joshi.ac.jp/column_back/img/201712.pdf,(参照 2025-09-09)