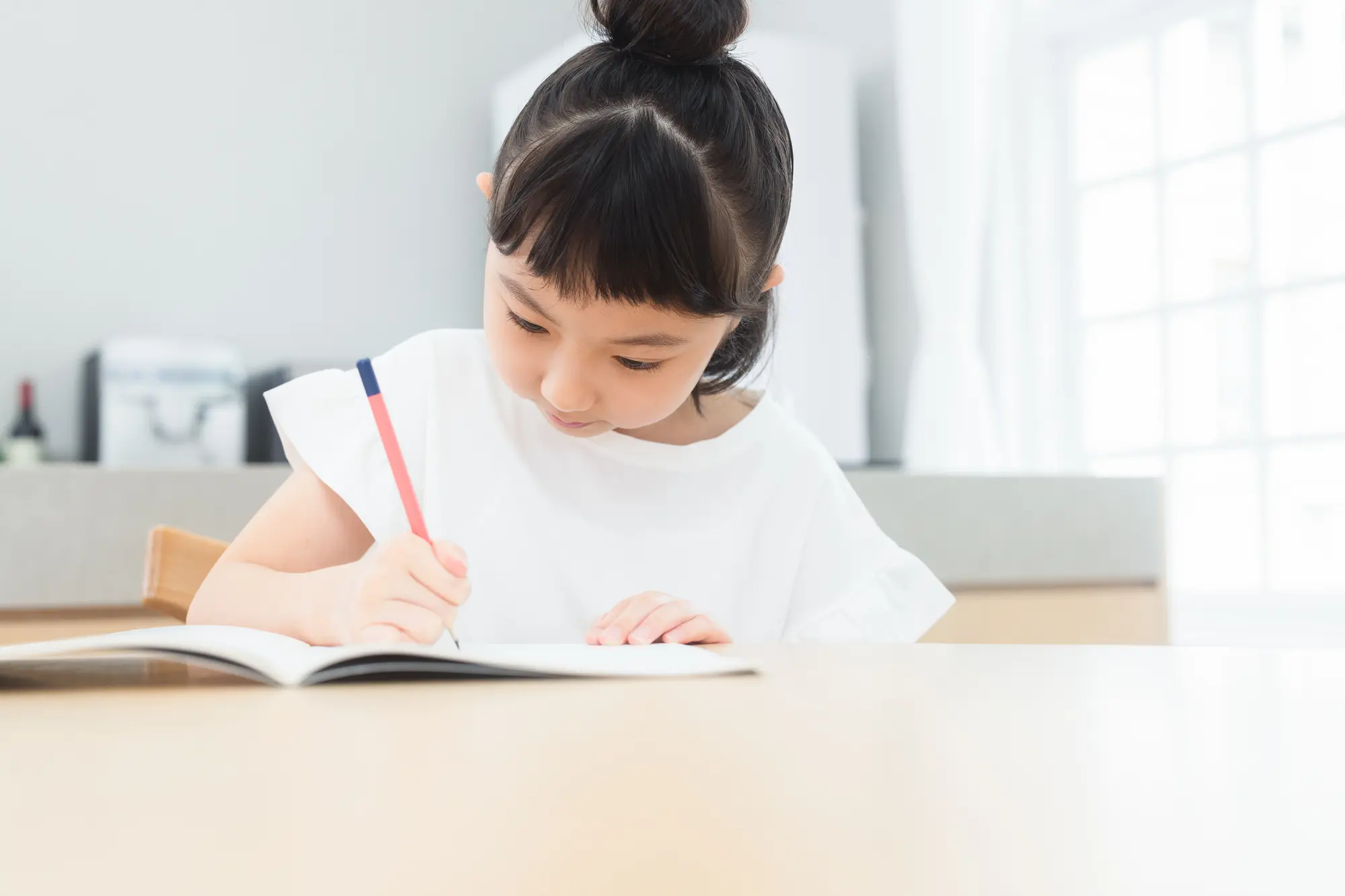「バランスチェアが膝に悪いって本当?」
「バランスチェアのデメリットは?」
子供の姿勢をよくしたいと考えて、バランスチェアの購入を考えるかたも多いでしょう。しかし、「膝を痛めないか心配」「正しい使い方が分からない」と不安に思っているかたもいるのではないでしょうか。バランスチェアは、背筋を自然に伸ばしやすくする工夫がされた椅子ですが、体に合わない高さや座り方を続けると膝や腰に負担がかかることがあります。
特に成長期の子供は、骨や関節が発達の途中にあるため、体格や年齢に合った使い方が欠かせません。正しい姿勢で使うことで、集中力や学習効率の向上にもつながります。この記事では、子供の体に合う座り方や高さ調整のコツを中心に、膝への負担を防ぐためのポイントを分かりやすく解説します。ぜひ、参考にしてください。
※2025年10月16日時点の情報です。
バランスチェアで膝が痛くなる原因とは
子供用のバランスチェアは姿勢を整える効果がある一方で、「膝が痛くなった」「すぐに疲れてしまう」と感じることもあります。これは椅子自体に問題があるというより、座り方や高さの調整が体に合っていないことが原因の場合が多いです。正しい姿勢で使えば、膝への負担を減らすことができます。ここでは、膝に負担がかかる主な理由を分かりやすく解説します。
姿勢を支えるバランスが崩れると膝に負担が
バランスチェアは「膝で支える椅子」と思われがちですが、実際には背筋を自然に伸ばすことで骨盤の角度を正しく保つためのサポート道具です。ところが、膝あて部分に体重をかけすぎると、関節や太ももまわりの筋肉に余計な力が入り、痛みや違和感の原因になります。特に成長期の子供は骨や筋肉がまだ柔らかく、無理な体勢を続けると膝関節に負担がかかりやすくなります。
高さが合わないと重心がずれてしまう
座面の高さや角度が合っていないと、上半身の重心が前に傾き、膝で体を支えようとする姿勢になります。すると、膝あてに過剰な圧がかかり、短時間でも痛みを感じることがあります。バランスチェアは見た目よりも高さ調整が重要で、足裏が床につかないまま使うと、姿勢が安定せず疲れやすくなるのです。
成長途中の関節には「休む時間」も大切
大人と違い、子供の関節や筋肉は日々発達しています。長時間座り続けると、筋肉が緊張したまま固まってしまい、膝や腰に違和感を覚えるケースもあります。1時間ごとに5〜10分ほど体を動かしたり、立ち上がってストレッチをすることで、体への負担を軽減できます。
子供の体に合った正しい座り方
バランスチェアを使うときに最も大切なのは、椅子の高さや姿勢を「子供の体に合わせる」ことです。正しい座り方を身につけることで、背筋が自然に伸び、膝への負担もぐっと減らせます。ここでは、成長期の子供が無理なく座れる姿勢のポイントを紹介します。
背筋をまっすぐに、体を前へ預けすぎない
バランスチェアは、骨盤を立てて背中を自然に伸ばすことで姿勢をサポートします。背もたれがないため、上体を前に倒しすぎると重心がずれ、膝や腰に負担がかかります。座るときは「おへそを少し引き上げるように」意識すると、上半身が安定しやすくなります。
膝あては「膝下(すね)」を支えるクッション部分
バランスチェアの前方にある「膝あて」は、実際にはすねの上部(膝のすぐ下)を軽く支えるクッションです。膝を押しつけて支える構造ではなく、上体の重さを分散させるための補助的な部分になります。おしり側に重心を置くのが正しい座り方です。膝やすねに強く圧がかかると痛みが出るため注意が必要です。
すねに力を入れすぎず自然に体を支える
バランスチェアでは足裏を床につけず、すねの一部をクッションに沿わせて体を支えます。すねに体重をかけたり過度な力を入れると筋肉がこわばりやすいため、軽く乗せるイメージで座るのがポイントです。背中と骨盤をまっすぐに保ち、上体が前に傾きすぎないよう注意しましょう。おしりでしっかり重心をとり、体がふらつかないよう意識すると安定します。座面や膝あての角度を調整できるタイプなら、子供の身長に合わせて傾きを変えると快適に使えます。
年齢・身長に合わせた高さ調整のコツ
子供の体は成長とともに日々変化しています。バランスチェアを使うときは、購入時のままにせず、体の大きさや姿勢の変化に合わせてこまめに調整することが大切です。高さや角度が合っていないと、膝や腰に負担がかかるだけでなく、集中しづらくなることもあります。ここでは、年齢や身長に合わせたバランスチェアの合わせ方を紹介します。
成長に合わせて「おしりの位置」を見直す
バランスチェアの高さを調整するときは、まずおしりが座面の中央よりやや後ろにくるようにします。深く座りすぎると体がのけぞり、浅いと上体が前に倒れやすくなるため、安定して背筋を伸ばせる位置を探すのがポイントです。おしりを置いたとき、体が自然にまっすぐになる高さが目安です。
膝下の角度は「直角より少し開く」が目安
膝あて(膝下を支えるクッション)は、すねが軽く斜めになる程度の角度が理想です。角度が急すぎると体が前にずれ、膝に力が入りやすくなります。逆にゆるすぎると上体が不安定になります。座ったときに「背筋が気持ちよく伸びる」と感じる位置を目安に、少しずつ角度を変えてみましょう。
定期的に高さを見直す習慣を
成長期の子供は数か月で姿勢のバランスが変わります。半年に一度は、おしりと膝の位置関係を見直し、必要に応じて高さを再調整してください。正しい姿勢を保つことで、集中力が続きやすくなり、学習環境もより快適になります。
子供に合うバランスチェアを選ぼう|使うメリットとおすすめ3選
子供の成長に合わせて正しい姿勢を保つことは、学習の集中力や体のバランスづくりにもつながります。バランスチェアは使い方を工夫すれば、膝への負担を抑えつつ、自然と背筋を伸ばすサポートができるアイテムです。ここでは、まずバランスチェアを使うことで得られる主なメリットを紹介し、そのあとにおすすめの商品を紹介します。
正しく使えば、すっと背筋が伸びる!バランスチェアのうれしい効果
おしりとすねで体を支えることで、背骨が自然に伸びやすくなり、正しい姿勢をキープしやすくなります。背中や腰への負担が減り、学習中も疲れにくくなるのが大きな特徴です。上体を起こした姿勢は呼吸が深くなり、集中力を高める効果も期待できます。使い方さえ合っていれば、体へのやさしさと姿勢サポートを両立できる頼もしい椅子です。
家で使いやすい!おすすめの子供用バランスチェア3選
対象:110cm~180cm
サイズ:62奥行き x 53幅 x 54高さ cm
座面の主な素材:張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム, 構造部材
フレームの主な素材:ブナ積層材、脚:ブナ天然木, 表面加工/ウレタン樹脂塗装
最大推奨重量:110 キログラム
「バランスラボ バランスイージー 通常フレーム」は、木工家具の産地・飛騨高山の職人が一つひとつ丁寧に仕上げている国産のバランスチェアです。北欧ノルウェーで誕生したデザインを、バランスマネジメント社のライセンスのもと日本で正規製造されています。膝面の高さは、標準付属パーツを使えば7段階調整も可能。座面が固定式のため、角度が安定しやすく、体への負担を感じにくい構造です。
対象:110cm~大人まで
サイズ:68奥行き x 48.5幅 x 64高さ cm
座面の主な素材:本体=天然木(ラッカー塗装)、座面=アクリル・ウレタンフォーム
目安の静止荷重:約80kg
「宮武製作所 プロポーションチェアキッズ 補助クッション付」は、補助クッション付きで子供でも安定して座れるモデルです。ネジで段階的に高さを変えられる構造になっており、成長に合わせて細かく調整できます。明るいライムカラーと丸みのあるフォルムが特徴で、学習机との相性も良好です。正しい姿勢を維持しながら、やわらかな座り心地を求める家庭におすすめです。
目安の静止荷重:約80kg
木製フレームとキャスター付きのバランスチェアで、リビング学習にもなじむナチュラルなデザインが特徴です。すねを支えるクッションがしっかりしており、膝や足に負担をかけにくい構造です。人間工学に基づいて設計されており、体を三点で支える構造で、バランスチェアには珍しく足置きがあるタイプです。シンプルながら使いやすく、初めてのバランスチェアにも選びやすいモデルです。
まとめ|バランスチェアは膝に悪い?正しく使えば体にやさしい座り方
バランスチェアは、膝や腰に負担をかける椅子ではありません。大切なのは、子供の体に合った高さや角度に調整し、正しい姿勢で座ることです。おしりとすねで体を支えることで、背筋が自然に伸び、長時間の学習中も呼吸しやすくなります。
一方で、高さが合っていなかったり、膝あてに体重をかけすぎたりすると、痛みや疲れを感じることもあります。そのため、子供の成長に合わせて高さ調整や座り方を工夫しながら使うことで、体にやさしい姿勢づくりが続けられます。
正しい使い方をすれば、バランスチェアは姿勢の習慣づくりを助け、集中力を高める良いサポートアイテムになります。家庭で取り入れる際は、無理をせず、楽しく座る時間を一緒に工夫していきましょう。
#バランスチェア #膝に悪い #知育 #知育玩具 #知育ママ #5歳 #6歳 #低学年
参考文献
みやしょう接骨院.“子どもの姿勢改善の重要性”.https://miyashou-sekkotsuin.com/column/detail/20250912113042/,(参照 2025-10-16)